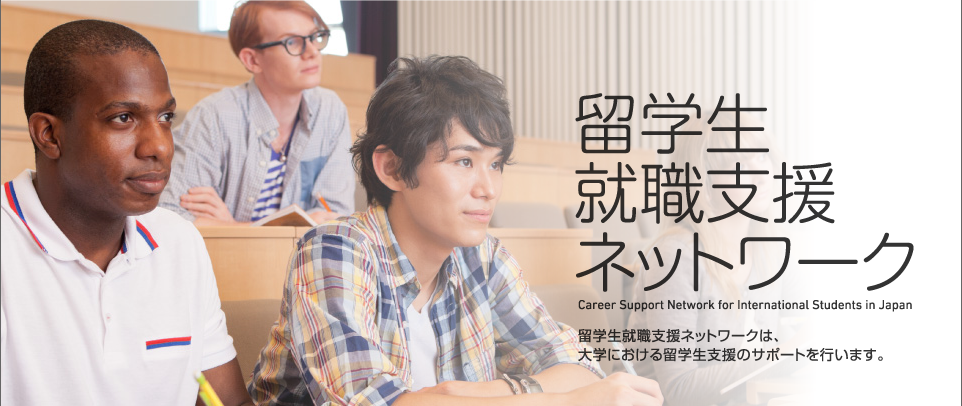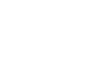留学生就職支援の現状
[3]-1 企業の採用動向
めまぐるしく動く国際的な経済情勢の中、多くの日本企業は更なる成長戦略を求めて、生産の基盤や販路拡大のための拠点を海外にも求めています。経済産業省の統計によると、現地法人企業数が1995年度は10,416社でしたが、2022年度は24,415社にまで増加し、特にアジア地域においては、1995年の4,600社から2022年は16,547社と3倍以上に増えており、このような日本企業の海外進出の動きはアジアだけでなくNIEs域内BRICsへの進出も急激に伸びています。
アジア諸国への進出当初、こうした海外拠点は「生産の現場」として捉えられてきましたが、近年は進出先の経済成長に伴い、「市場」としての姿にも注目が集まっています。海外での売上高についても、1995年度は94.8兆円でしたが2022年度は361.5兆円まで増加し、特にアジア地域においては、1995年の24.5兆円から2022年は162.9兆円と6.6倍に増えており、北米の119.6兆円を上回る市場となっています。
また、我が国の人口は2004年をピークに減少傾向の局面に入り、将来の持続的な成長を確保するためには、一人当たりの生産性の向上などの新たなイノベーションが求められています。
一方、アジア等諸外国に目を向けると、豊富な若年人口と各国の大学に在籍する優秀な学生が数多く在籍しており、こうした人材の獲得は今後の企業の成長、とりわけアジア等に進出しようとしている企業にとって重要な経営資源となると考えられています。
このような背景から、近年マスコミ等で先進企業による外国人採用の活発化が報道されています。大手製造業を始めとし、小売業、サービス業、中小企業において外国人採用を採用枠の1割程度や数十名単位で採用を行う企業も現れています。
[3]-2 企業の採用目的
〈日本企業による高度外国人材※の採用理由〉
①国籍不問採用
②海外展開要員採用
③ダイバーシティ採用
④人手不足による採用
※「高度外国人材」とは、就労可能な在留資格である専門的・技術分野の在留資格を有する外国人労働者(4年生大学の卒業資格を持つ者及びまたはそれと同等の知識を必要とする職に就いている者)
一般的に日本企業による高度外国人材の採用理由・享受するメリットとして大きく3つに分類できると考えられます。
①国籍不問採用とは文字通り「国籍に関係なく優秀な人材を求める」という採用方針で、企業の競争力保持のために高度外国人材の受入推進が政府、産業界から問題意識として提起される前から存在しているものです。
②海外展開要員については、海外との架け橋となる人材のことであり、外国人留学生が持つ言語能力や出身地と日本との両方の事情や文化に明るいといった「母国と日本との良好な関係構築への貢献」を期待するものであり、外国人留学生の出身国への進出や取引、来日する外国人観光客に対するインバウンド需要に対応する目的と、外国人留学生の英語能力を活用した外国人留学生の出身国に関わらない海外市場の開拓、拡大の目的の2種類に分けられます。
③ダイバーシティ要員とは、文化背景の異なる人材のことで比較的最近になって評価されるようになった考えです。あえて多様な背景をもつ人材を意識的に社内に取り込むことにより、組織活性化と商品などの多国籍な付加価値の創出などを促すというものです。
④人手不足による採用については、特定の業界で日本人学生の採用が困難であり、日本語の堪能な外国人留学生を採用するというもので、外国人留学生の能力を期待するという観点ではなく、日本人の能力(日本語能力)にできるだけ近い人材を採用するというものです。
高度外国人採用の日本での採用については、一部の専門職を除けば1990年後半に主に外資系企業や中堅IT企業が中途採用を主とした即戦力の人材の採用を始め、2005年頃から大企業や中堅企業が外国人の新卒採用を始めました。2007年頃にアジアの成長の加速とともに上記分類②の「海外展開要員」を求める企業が増えてきました。2010年からは、これまで生産拠点としての位置づけから、消費者の所得増で急激に発展する市場としてアジアやBRICsを始め日本企業が海外に進出するために戦略的に必要な、上記分類①、③に該当する「グローバル人材」のニーズが高くなり、優秀な高度外国人材の採用拡大はもとより、日本人社員の国際化を目的とした採用・研修が行われるようになってきています。
留学生、日本人学生双方に企業から求められるものとして、日常的な業務遂行能力のレベルアップに加え、グローバル社会を勝ち抜くための、英語や中国語などの語学力はもちろんのこと、異文化理解を含めたグローバルコミュニケーション能力が挙げられます。